前回の続きで子どもの歯の話です。
本日の話題は、
1歳-1歳半児 上の歯、真ん中周囲の虫歯に注意する。
1歳半-2歳児 歯の外傷が増加してくる。親御さんの仕上げ磨きの確認。
2歳-3歳児 3歳児健診で新規の虫歯や歯並び等の確認。
を注意します。では1つずつ詳しく確認していきましょう。
1: 1 歳-1歳半 (乳臼歯萌出期)
この時期はまだ夜間授乳や添い乳、添い寝でのミルクをしている児がまだ多いです。そのため、夜間授乳をしている場合、前回の注意点で説明した、上の歯の真ん中周囲に虫歯が出来やすくなります。
親御さんは、この時期以降はしっかりと歯磨きをしてあげる必要があります。
2: 1歳半-2歳 (乳犬歯萌出期)
この時期はひとり歩きが可能になりますので、転倒による歯の外傷が増加します。
まず歯の外傷の説明をします。
1-3歳は外傷の好発年齢であり、2:1で男児に多いです。
部位は上の歯の前歯(上額中切歯)が約80%です。時間帯は午前中に多く、室内のテーブルやソファーから転倒が原因となることが多いことが報告されています。
転倒して前歯の色が変わってしまうことがあります。外傷による力が歯に加わり、歯の中の血管が出血をおこすことで生じます。この出血が変色の原因になります。
受傷から8か月以内に自然に回復することが多いといわれていますが、8か月をこえても改善がなければ戻らない可能性が高いです。
変色した歯は壊死してしまうことがあるため、外傷により歯が変色した場合は必ず歯科の受診をしてください。
またこの時期は、親御さんが1日1回、仕上げみがきをしないと虫歯の予防にならないこともわかっています。必ず仕上げ磨きをするようにしましょう。
3: 2歳-3歳 (乳歯列完成期)
この時期は歯磨きの習慣がきちんと定着する期間であり、規則正しく食事をとることが虫歯の予防になることを再確認します。3歳健診で現時点での虫歯の有無を確認し、ある場合は治療となります。
噛み合わせについて相談されることが多いので説明します。
3歳頃までは歯並びや、噛み合わせは変化します。そのため一番奥の乳歯がはえて噛み合うまでは経過観察となります。
1歳半健診で上下の歯の噛み合わせが逆であることを質問されることが多いですが、自然と改善することがあるため3歳までは様子をみます。3歳を過ぎても前歯の噛み合わせが逆(反対咬合)、前歯の歯並びがデコボコ(叢生)である場合は歯科の先生に相談となります。3歳健診で歯並びについて心配な場合は相談してみるとよいでしょう。
指しゃぶり、爪を噛むなどの癖は3歳を超えると歯並びに影響しますのでやめられるように指導します。
指しゃぶりの説明をします。指しゃぶりは精神を安定させる効果があり、もともとお母さんのお腹にいたときから赤ちゃんは指しゃぶりをしています。
生まれて2か月後くらいから、手をよく動かすようになり指しゃぶりがはじまります。
ずりばいのような手と足の協調運動が出来るようになってくると、本格的な指しゃぶりとなります。
この時期の指しゃぶりは、発達の経過おこることですので全く問題はありません。
9-10か月健診の記事でも少し記載があります。確認してみてください。
しかし、3歳を超えて指しゃぶりをしている場合は、前歯が前に出る「出っ歯」を含め、歯並び全体が悪くなることがわかっています。指しゃぶりだけでなく、爪を噛む、おしゃぶりをすることは歯並びに影響しますので注意が必要です。
3歳までの子どもの歯について説明しました。次回は3歳以降の注意点を説明する予定です。
写真は2月2日に参加してきた小児診療多職種研究会の看板です。
会長の倉重先生から講演依頼をいただきましたので発表してきました。
私は以前に子どものカフェイン摂取に関して警告をする目的で発表をしてきた経緯があり、その活動を見てくださったようです。子どものカフェイン摂取についても今後記事にしていきますね。
小児診療多職種研究会は今回初めての参加でした。
この研究会は医師だけでなく、看護師や薬剤師、保育士等様々な職種の方が発表をしていました。
その中でも、イギリス発祥のホスピタル・プレイ・スペシャリスト(HPS)という職種について少し説明します。
病気の子どもに対する援助全般を行うもので、主に入院している子どもたちが受ける処置(注射や点滴、画像検査)をいかにして苦痛なくうけることができるか、また入院中の生活を「遊び」を通じてサポートするかというのがHPSの仕事内容です。
このHPSは看護師や保育士が本来の業務に加え追加で資格をとり子どものために尽力されています。
発表されている方の中には、HPSの本場イギリスで留学をされ報告している看護師や保育士の方もおり、私もモチベーションが上がりました。
HPSの発表内容の中には、私のクリニックでも実践できるテクニックが多くあり非常に勉強になりました。
少しでも子ども達の採血に対しての痛みのケアに繋げていければと思います。
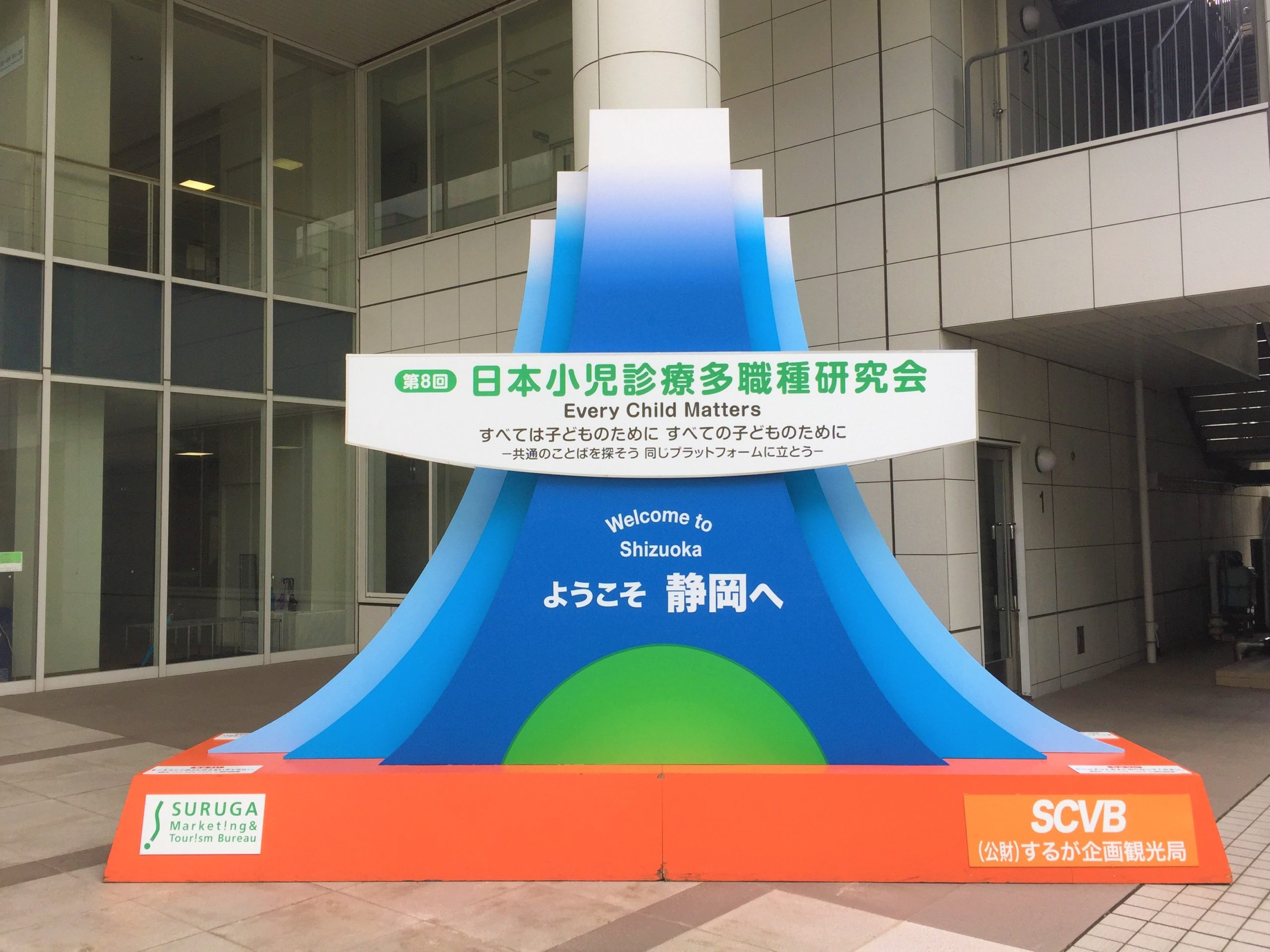















改めて記事を読み返しています!
こどものカフェイン摂取についての記事、もしまだでしたら今後よろしくお願いします。
また、アルコール摂取についてもご研究の方がいらっしゃって、論文を気に留めるお時間がありましたらお願い致します。
論文を読んで記事にまとめていただき、ありがとうございます。長年研究されている分野だったり、マイノリティの分野だったりするとなかなか読むのが大変なこともありますよね、、、。何事も根気が必要なんでしょうね。
こうママ様
そうでした。カフェインの記事完全に忘れていました。ここ数年で若年層のカフェイン中毒が多数報告され、以前は日本での報告がほとんどなかったのが、日本でかなりの報告数になってきています。
私が論文発表した時とカフェイン中毒は本当に状況が変わりました。埼玉医科大学の救命科の教授がカフェイン中毒に関しては有名で、去年に前向き研究をスタートしていたと思います。確認してみますね。
アルコール摂取に関してもですね。これは日本での報告は誤飲しかありませんので海外がメインになると思います。誤飲対策としてなにか記事を作成できればと思います。
論文を読むことはニュースを読むのと同じなので決して大変ではないです。空き時間にさらっと目を通すだけなので慣れだと思います。ただ、それを記事にするとなると一旦頭の中で整理して文章に書きなおすので少しまとまった時間がいる感じでしょうか。
記事のアイデアありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
能登
同じ記事からのコメント失礼いたします。カフェインの記事、ありがとうございました。
こちらの記事でも記載されています通り、転倒による口の中の出血がすでに2回ほどありました。歯の様子は注意深く見守りたいと思います。
小児検診の記事にもありましたが、指しゃぶりについて。3才までは様子見でもよいとのことですが、できればすこし早めに卒業できるようにしていければなぁと思っていました。直接お伺いする機会がなくなってしまったので、もし可能でしたら、卒業にむけてどういった指導をされていたかを教えていただけないでしょうか。
個性にもよるので難しいかもしれませんが、ご検討いただけますと幸いです。
こうママ様
コメントありがとうございます。
指しゃぶりについては健診でよく質問されるものでもっとしっかり説明をしておくべきでした。コメント欄ですが、情報を補足していきましょう。
まず、指しゃぶり自体は3歳で約15-20%の子がまだ指しゃぶりをしているというデータがあります。5歳をこえても約10%くらいが残存しているというデータもあるくらいです。
なのでまず我が子が指しゃぶりをしているからといって親が焦る必要はありません。落ち着いて対応していきましょう。
では、なぜ指しゃぶりをするのでしょうか。一説にはお母さんのお腹の中にいる時に赤ちゃんは指しゃぶりをしながら羊水を飲んでおり、安心安全の姿勢であるといわれています。
実際指しゃぶりをするとホルモンが分泌され落ち着くという事実もあります。
そのため、生後6か月を過ぎて、完全母乳のお子さんであれば、遊び飲みを経験すると思います。この時期から安心を得るための吸啜行為が生理現象としておきます。
つまり、お子さんとしては、指しゃぶりをすることで不安やストレスを回避するため、そして安心安全で落ち着くための行動として指しゃぶりをするということになります。
指しゃぶりは悪い事ではありませんから、卒業にむけて決して子供を叱ったり、指をなめて恥ずかしいねなどと声をかけることは絶対にしてはいけません。
自己肯定感が下がってしまい、かつ安心を求めての行動でやめられないという悪いループになってしまいます。
ではどうやって指しゃぶりの卒業へむけて私がアドバイスをしているかというと、安心安全のための行為を違うもので代替しましょうと説明しています。
ほとんどのお子さんが寝る前に指をしゃぶって寝付くというパターンが多いと思います。そこで、よく指をしゃぶる親指をママやパパが握ってあげます。
そして反対の手に自分の好きな人形やミニカー(男子はだいたいミニカーか電車のおもちゃ)をもたせることで代替していきます。
自分もそうでしたが、ボロボロになった人形や掛布団など、寝る前にこのアイテムがあると落ち着くというものがあったかと思います。
自分が落ち着くための行為を指しゃぶりから物とママ、パパの手に代替していくというやり方を説明しています。
亜鉛華軟膏のような軟膏を親指に塗ると、苦いから指しゃぶりをするのをやめるよという指導をされた方がいるかもしれません。というか私は小児科になり習いました。
ですが、我が家で試してみましたが予想通り逆効果でした。安心安全を求めて指しゃぶりをして、さらに苦い味でストレスがかかり泣きじゃくりました。
なので男子であれば必ず好きな車や電車のおもちゃ、女子は好きな人形などがあると思いますのでその代替できる物と一緒にいることでストレスを緩和しゆっくり卒業へ促すのがよいと私は考えます。
参考になりましたでしょうか。またなにかあればコメントでご指摘ください。
今後ともよろしくお願い致します。
能登
詳細な情報ありがとうございます。
少しずつタイミングみて試していきたいと思います。
夫にも読んでもらって、共有して進めたいと思います。
取り急ぎ、御礼まで!